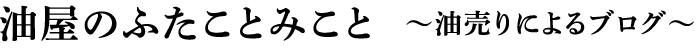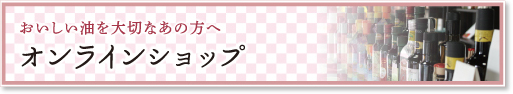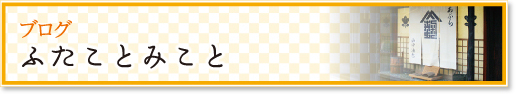11月8日の日曜日、京都府大山崎町の公民館で
油の歴史に新しい灯が点されました。

このお燈明は、大山崎町の方々が、大山崎の畑で収穫したエゴマを
大山崎で搾油し、そしてその油に灯を点されたものなのです。
大山崎と油の関わり、それは離宮八幡宮様のご由緒にも、
—貞観年間、時の神官が神示を受けて
「長木(ちょうぎ)」という搾油器を発明し
荏胡麻(えごま)油の製油を始めました— とあります。
シソ科の一年草である荏胡麻は、
その実(種)が胡麻のようであることから「エゴマ」と呼ばれていますが、
もともと「荏(え)」と言う名前で、古くから食用にされてきました。

モノの名前は単純であるほど古いものだという説があります。
「目」「手」など、一文字で表せるものが古くから使われている言葉の例です。
そうすると「荏」は、古くから生活に関わってきた植物だと考えられます。
大山崎は、今から1150年前、荏胡麻油が日本で初めて搾油された地であり、
室町時代には油座がおかれ、
全国の搾油と販売の独占権を握るようになったのです。
さて、現代の大山崎の話に戻ります。

これらのエゴマは、春の終わりごろに種まきをされ、
班ごとに当番をきめて、暑い夏の日にも水遣りや雑草抜きをされるなど、
手塩にかけて育ててこられ、先日収穫されたエゴマです。
それを特製のこの搾油機で搾り出します。
(アダピスのとーじ・まサトシ氏制作)

圧をかけて油を搾り出しまが、この細い管にはストローが使われています。

そしてその油に灯が点されたわけです!
12月に離宮八幡宮様で御献灯が行なわれます。
油の神様も、大山崎の人々が丹精こめて育てた荏胡麻の油でのお燈明を
喜んでくださるだろうな、と今からワクワクしています。